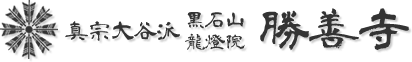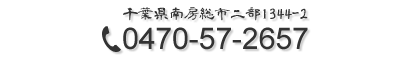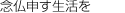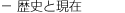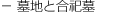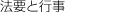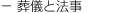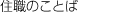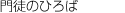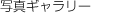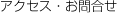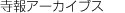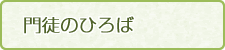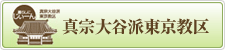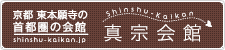弥陀の本願信ずべし
弥陀の本願信ずべし
2018.05.23
「『弥陀の本願信ずべし』という言葉がなぜか突然思い浮かび、思いがあふれ出てきました。」と、寺を訪れた女性が告げてきました。
その方は、ご主人を亡くされてた後、仏教に生き方を求め聞法会や月曜朝のお勤めなどに参加されるようになりました。
その日はご主人の墓参りに詣で、たまたま本堂にいた私を見つけ話しかけてきたのでした。
「では、それを文章にしてください」とお願いし、下記の文章が届けられました。
弥陀の本願信ずべし
最近、私の周りで顔見知りの人が何人か亡くなり、ショックが大きく、いたたまれない気持ちになりました。
健康で何事も無く明日が迎えられれば良し、そう願って生きていますが、明日がどうなるか?なんて誰にもわからない。「今日が人生最後の日になるかもしれない。だから今を大事にし生きる」そう感じました。
幸、不幸も自分の尺度で感じることで、幸せだと思っている事も不幸だと思っている事も、本当はそうでは無いんじゃないかと思います。だって本当の幸せ、不幸が分からないからです。何事も自分基準で考えるので、思うように行かない時は苦しく悲しくて・・・、また、思うようにいった時は嬉しくて「これが幸せなんだ」と思ったりして・・・。人生に一喜一憂する私です。
「幸せになりたい、不幸になんかなりたくない」と願う度に、自分では気が付かないうちに人を傷つけていたり、思うようになかなか生きられないし、努力も無駄なのか?解放されたい、助けてほしい、そんな思いでした。「生きる事ってそんなに苦しいの?」と。
でも、教えを聞いていく度に「気負わずにそのまま生きればいいんだ」、失敗した時は反省し、本願(生きる本当の喜び)を学ばせていただく。そうやって一日一日を生きて行く。
これからは感謝の気持ちで「アミダ様」に掌を合わせたいと思います。
人間の力なんてたかがしれています。どんなにえらぶっても「お釈迦さま」の掌の中です。
だって、あの世もこの世も宇宙も「アミダ様」の世界ですから。
2018.5.20
「弥陀の本願信ずべし」 は、親鸞聖人が『正像末和讃』の巻頭に「康元二歳丁巳二月九日夜寅時夢告云」と掲げた和讃の一句目です。
弥陀の本願信ずべし
本願信ずるひとはみな
摂取不捨の利益にて
無上覚をばさとるなり
「この一首は、聖人が85歳のとき、すなわち後深草天皇の康元2年2月9日の夜、夢の中に感得された和讃で、他力の信心をすすめて一帖の大要を示されたものである。」
高木昭良著『三帖和讃の意訳と解説』(永田文昌堂)
「(夢告は、)夢告になるまで、問つづけ、問いつめられたということです。」、「この康元二年、聖人85歳のときの夢告は、末法五濁の現実を悲痛され、その世の人びとの救いを念じつづけいられたなかで、聞き取られた者といわれいます。たしかに、そういうことであったのだろうと思われます。
ただ、私には、この康元2年という年が心にかかるのです。つまり、その前年の5月29日、聖人は、子息善鸞を義絶されているのです。84歳という、人生も最晩年になって、信頼し、自らの代理として関東に送りだしたわが子が、あろうことか、その信頼を裏切り、苦しい生活の中で念仏ひとすじに生きている関東の念仏者たちを混乱におとしいれた、その事実を知って、念仏の僧伽のために、あえてわが子を義絶された、その悲しみがどんなに深いものであったか、今までの自分の一生の歩みが、すべて徒労感のなかに消えていくような絶望があったと思えるのです。しかも、この頃、日蓮聖人による念仏批判に、多くの念仏者立ちが動揺を深めていたということもあります。
親鸞聖人は、その歩みの原点に立ちもどり、再び聖徳太子の前に身をひきすえて、根本から問い直し、尋ねられたのだと思います。そしてそこで、あらためて、全身をもって聞き取り、うなずかれたのが、この「弥陀の本願信ずべし」の一首であったと思われるのです。この一句こそが正像末をつらぬいて人間が真に依るるべき道であることを、うなずき直されたのだと思います。」
宮城顗著『和讃に学ぶ 正像末和讃』(東本願寺出版部)
この御和讃は、夢の中に感得せられたものです。それが因縁になって「正像末和讃」の御製作を始められたのです。「正像末和讃」は、
釋迦如来かくれましまして
二千余年になりたまふ
正像の二時はおはりにき
如来の遺弟悲泣せよ
という御和讃から始まりまして、
如来大悲の恩徳は
身を粉にしても報ずべし
師主知識の恩徳も
ほねをくだきても謝すべし
まで五十八首。それから引き続いて「佛智疑惑和讃」二十三首があります。その後「聖徳太子奉讃」十一首の御和讃を付けられたのであります。
大分前のことでありますが、曽我量深君が、親鸞聖人は八十過ぎてからまだ本願の疑いがあったのだ。時々疑いの心が起きておられたのだ、と言うた。なぜかと言うと、この『正像末和讃』の最初の御和讃を見るとそれが分かる。どぅ分かるか。「弥陀の本願信ずべし」という声が聞えるのだ。「弥陀の本願信ずべし」という声は、疑うておる者に対するお言葉である。疑いということがなければ、信ずるという言葉は出て来ん。聖人が夢の中に感得せられたお言葉、「弥陀の本願信ずべし」というその御和讃を感得せられる時の、聖人の胸の中に疑いがあったのだと言ったことがあります。
『御伝鈔』を読みますと、「真宗紹隆の大祖聖人、ことに宗の淵源をつくし、教の理致をきはめて、これをのべ給ふに、たちどころに他力摂生の旨趣を受得し、飽まで凡夫直入の真心を決定し、ましましけり」、と書いてあります。そうすると、はっきり御信心の眼が開けていらっしやった筈である。疑いが晴れて、本願を信じておいでになっておられたのであります。勿論、五十二才の歳、筆を染めさせられた『教行信証文類』には、聖人の御信心の喜びが書いてある。それから『浄土和讃』『高僧和讃』の中にも、信心のお喜びが書いてあります。しかるに八十二才になって、どうして疑いが出たか。これが問題になる。この「正像末和讃」五十八首が済んでから、
佛智うたがふつみふかし
この心おもひしるならば
くゆるこゝろをむねとして
佛智の不思議をたのかべし
という、あの「佛智疑惑和讃」が書かれました。何んであゝいう御和讃が出たのだろうか。聖人は御自分の心の中に、疑惑ということがあるとなぜおっしゃったのだろうか。そこでなんであります。私等が何かものを考えるということも、感ずるということも、自分の胸の中にないことは考えられないものである。胸の中にあるから、考えたり感じたり出来る。だから盗人の境界を考えるのも、やはり盗人根性があるからです。だから自分の心の中に全然疑いの影がない者は、疑いということも考えられないものです。
「夢告和讃講話」暁烏 敏 著『和讃講話集 下』(凉風学舎)
、