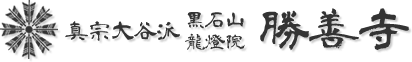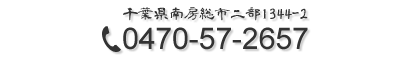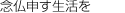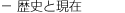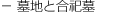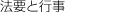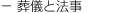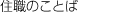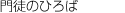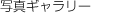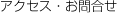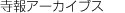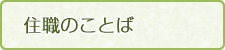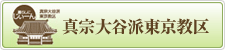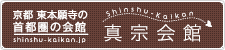жі•дәӢгӮ’еӢӨгӮҒгӮӢеҝғ
жі•дәӢгӮ’еӢӨгӮҒгӮӢеҝғ
2019.05.10
з„Ў(гӮҖ)ж…ҡ(гҒ–гӮ“)無愧(гӮҖгҒҚ)гҒ®гҒ“гҒ®иә«гҒ«гҒҰ
гҒҫгҒ“гҒЁгҒ®гҒ“гҒ“гӮҚгҒҜгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ©гӮӮ
ејҘ(гҒҝ)йҷҖ(гҒ )гҒ®еӣһ(гҒҲ)еҗ‘(гҒ“гҒҶ)гҒ®еҫЎеҗҚ(гҒҝгҒӘ)гҒӘгӮҢгҒ°
еҠҹеҫігҒҜеҚҒ(гҒҳгҒӨ)ж–№(гҒҪгҒҶ)гҒ«гҒҝгҒЎгҒҹгҒҫгҒҶ
гҖҺжӯЈеғҸжң«е’Ңи®ғгҖҸгӮҲгӮҠ
вҖ»гҖҢз„Ўж…ҡ愧無гҖҚгҒҜгҖҒж…ҡ愧гҒҢз„ЎгҒ„гҖҒзҪӘгӮ’жҒҘгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зҹҘгӮүгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҖӮ
е№іжҲҗгҒӢгӮүд»Өе’ҢгҒ«е…ғеҸ·гҒҢж”№гҒҫгӮҠгҖҒеҚҒйҖЈдј‘гӮӮзөӮгӮҸгӮҠгҖҒж—ҘеёёгҒҢжҲ»гҒЈгҒҰгҒҫгҒ„гӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ•гҒҰгҖҒжҜҚгҒ®е‘Ҫж—ҘгҒҢиҝ‘гҒҘгҒ„гҒҰгҒҚгҒҹжүҖзӮәгҒӢгҖҒжқҫеҺҹзҘҗе–„её«гҒ®ж¬ЎгҒ®ж–Үз« гҒ«зӣ®гҒҢжӯўгҒҫгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖжҜҚгҒёгҒ®зҘҲеҝө
дә”жңҲдёүж—ҘгҒЁгҒ„гҒҲгҒ°жҲҰеҫҢгҒҜжҶІжі•иЁҳеҝөж—ҘгҒЁгҒ—гҒҰеӣҪж°‘гҒ®еӨ§еҲҮгҒӘзҘқж—ҘгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒе®ҹгҒҜгҒ“гҒ®ж—ҘгҒҜз§ҒгҒҜеҝҳгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®еҮәжқҘгҒӘгҒ„жҜҚгҒ®е‘Ҫж—ҘгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮе№ҙгӮ’йҮҚгҒӯгӮӢгҒ«еҫ“гҒ„дәЎжҜҚгҒёгҒ®жҖқж…•гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒӢгҖҒгҒ“гҒ®й ғгҒҜжҜҚгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢзҘҲеҝөгҒҢеҲҮе®ҹгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰжқҘгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮз§ҒгҒ®жҜҚгҒҜеӣӣеҚҒжүҚгҒ§гҒ“гҒ®дё–гӮ’еҺ»гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгӮӮгҒ—жҜҚгҒҢзҸҫеңЁгӮӮгҒ“гҒ®дё–гҒ«з”ҹгӮ’еҫ—гҒҰеұ…гӮүгӮҢгӮӢгҒЁгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒгӮӮгҒҶеҸӨзЁҖгӮӮгҒҷгҒҺгҒҰи…°гӮӮжӣІгҒЈгҒҹзҷҪй«ӘгҒ®иҖҒе©ҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰеұ…гӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«зӣёйҒ•гҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҒ—гҒӢгҒ—гҒқгҒҶгҒ„гҒҶиҖҒе©ҶгҒ®е§ҝгҒ§з§ҒгҒҜиҮӘеҲҶгҒ®жҜҚгӮ’жғіеғҸгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ©гҒҶгҒ—гҒҰгӮӮеҮәжқҘгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ„гҒӨгӮӮиҮӘеҲҶгҒ«з”ҹгҒҚгҒҰжҮҗгҒ—гҒҸжҖқгҒ„еҮәгҒ•гӮҢгҒҰгҒҸгӮӢжҜҚгҒҜдёүеҚҒд»ЈгҒ®иӢҘгҒ„е§ҝгҒ®жҜҚгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ—гҒҰдҪ•е№ҙгҒҹгҒЈгҒҰгӮӮе°‘гҒ—гӮӮе№ҙгӮ’гҒЁгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®гҒ“гҒЁгҒҜжҜҚгҒҢеӣӣеҚҒжүҚгҒ®иӢҘгҒ•гҒ§гҒ“гҒ®дё–гҒ®е§ҝгӮ’ж¶ҲгҒ—гҒҰгӮӮгҒҶгҒқгҒ®дёҠгҒҜгҒ“гҒ®ең°дёҠгҒ§е№ҙгӮ’гҒЁгӮүгӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒқгҒ®е§ҝгҒҜиҰӢгҒҲгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒжҜҚгҒҜж°ёйҒ гҒ«з§ҒиҮӘиә«гҒ«з”ҹгҒҚгҒҰзҸҫеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮз§ҒгҒҜгҒ“гҒ®жҜҚгҒ®жүӢгҒ«ж”ҜгҒҲгӮүгӮҢгҒҰд»Ҡж—ҘгҒҫгҒ§е№ҫеәҰгҒӢеҮәйҖўгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹз”ҹжҙ»гҒ®гҒ„гҒҚгҒҘгҒҫгӮҠгӮ„з”ҹе‘ҪгҒ®еҚұж©ҹгҒ«гӮӮиҮӘжҡҙиҮӘжЈ„гҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүе…ҚгӮҢгҒҰгҖҒе·ұгӮ’жҚЁгҒҰгҒҰдҪ•гӮҲгӮҠгӮӮзҸҫе®ҹгҒ®дәӢе®ҹгӮ’еҸ—гҒ‘гҒЁгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’еӯҰгҒ°гҒ—гӮҒгӮүгӮҢгҒҰжқҘгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮз§ҒгҒ®зҲ¶гҒҜжҷ©е№ҙгҒ«гҒҜеҶҶжәҖгҒ¶гӮҠгӮ’иҰӢгҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжҖ§жқҘиһҚйҖҡгҒ®гҒҚгҒӢгҒӘгҒ„гҖҒгҒқгҒ®зӮ№гҒҜз§ҒгӮӮзҲ¶гҒ®жҖ§ж јгӮ’гҒқгҒ®гҒҫгҒҫгҒҶгҒ‘гҒҰжқҘгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒй ‘еӣәгҒӘдёҖеҫ№гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮиІ§гҒ—гҒ„еҜәгҒ®еқҠе®ҲгҒЁгҒ—гҒҰгҒ“гҒ®зҲ¶гҒ«е«ҒгҒ—гҒҰжқҘгҒҹжҜҚгҒ®з”ҹж¶ҜгҒҜгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢиӢҰеҠҙгҒҢеӨҡгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮжҒҗгӮүгҒҸз§ҒгҒ®жҜҚгҒҜгҒ“гҒ®дәәз”ҹгҒ«еёҢжңӣгҒӘгҒ©гҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҒӢгҒ‘гӮүгӮӮжҢҒгҒЎеҗҲгҒӣгҒҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒӢгҒЁжҖқгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮе…ЁгҒҸеҝҚеҫ“гҒ®дәҢеӯ—гҒҢгҒқгҒ®жӯ©гҒҝгҒ§гҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒқгҒ®еҝҚеҫ“гҒ«еҫҢжӮ”гҒ®и·ЎгӮ’е°‘гҒ—гӮӮж®ӢгҒ—гҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮжҜҚгҒҜжҜҚгҒӘгӮҠгҒ«гҒ“гҒ®дё–гҒ«гҒ“гҒ®дё–д»ҘдёҠгҒ®дәәз”ҹгҒ®ж„Ҹзҫ©гӮ’иҰӢеҮәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮз„ЎеёёгӮ’з„ЎеёёгҒЁзҹҘгҒЈгҒҰгҒ“гҒ®дё–гҒ«жұӮгӮҖгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҒӣгҒҡгҖҒгҒ—гҒӢгӮӮгҒ“гҒ®дё–гӮ’ж„ӣгҒ—гҒҰе‘ҪйҷҗгӮҠгҒ«гҒ“гҒ®дё–гҒ®зҸҫе®ҹгҒ«д»•гҒҲжҢәиә«гҒ—гҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жҜҚгҒ®жӯ»гҒҜз§ҒгҒҢз”°иҲҺгҒ®йғ·йҮҢгҒ®дёӯеӯҰгӮ’еҚ’гҒҲгҒҰгҒҹгҒҫгҒҹгҒҫдә¬йғҪгҒ«еҮәгҒҫгҒ—гҒҹеҪ“еҲқгҖҒдёҖгғөжңҲеҫҢгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеҪ“жҷӮж—ўгҒ«жҜҚгҒҜз—…еәҠгҒ«гҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ®гӮ“ж°—гӮӮгҒ®гҒ®з§ҒгҒ«гҒҜгҒқгӮҢгҒҢгҒқгӮ“гҒӘгҒ«йҮҚз—…гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒЁгҒҜгҒӨгӮҶзҹҘгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮиҮЁзөӮгҒ®еәҠгҒ«зҲ¶гҒҜжҜҚгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰйҒәиЁҖгҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒҹгҒҡгҒӯгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒӘгӮ“гҒ«гӮӮгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢжҜҚгҒ®зӯ”гҒҲгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮж¬ЎгҒ«зҲ¶гҒҜдә¬йғҪгҒ«еҮәгҒҹй•·з”·гӮ’е‘јгҒігҒҹгҒ„гҒҢгҒЁиЁҖи‘үгӮ’гҒӢгҒ‘гҒҰгҒҝгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒдёҖгғөжңҲеүҚгҖҒеҪјгҒ®еҮәзҷәгҒ®гҒЁгҒҚз§ҒгҒҜгҒ“гҒ®дё–гҒ®еҲҘгӮҢгӮ’жёҲгҒҫгҒӣгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮд»Ҹжі•гҒ®дёҖеӨ§дәӢгҒ®еӢүеӯҰгҒ«еҮәгҒӢгҒ‘гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒдјҡгҒ„гҒҹгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢгҖҒзҲ¶гҒӢгӮүиҒһгҒӢгҒ•гӮҢгҒҹжҜҚгҒ®жңҖеҫҢгҒ®иЁҖи‘үгҒ§гҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮе№ҫгҒЁгҒӣгӮ’йҮҚгҒӯгҒҰгӮӮгҒ“гҒ®жҜҚгҒ®иЁҖи‘үгҒ®еүҚгҒ«й ӯгҒ®дёҠгҒ’гӮҲгҒҶгҒ®гҒӘгҒ„гҒ®гҒҢз§ҒгҒ®д»Ҡж—ҘгҒ®е§ҝгҒ§гҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮд»ҠгҒ«гҒ—гҒҰдёҖеӨ§дәӢгҒҢдёҖеӨ§дәӢгҒЁгҒ—гҒҰиө·гҒҹгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒ“гҒЁгҒ«ж…ҡ愧гҒ®иҮігӮҠгҒ§гҒҷгҖӮе№ёгҒ„гҒ«д»Ҡе№ҙгҒ®жҜҚгҒ®жі•иҰҒгҒ«гҒҜгӮҒгҒҡгӮүгҒ—гҒҸйҮ‘жІўгҒ®пјҙеё«гӮ’гҒҠжӢӣгҒҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҮәжқҘгҒҰгҖҒжі•и©ұгӮ’гҒ„гҒҹгҒ гҒҸгҒ“гҒЁгҒҢеҮәжқҘгҒҹгҒ®гҒҜдҪ•гӮҲгӮҠгҒ®е–ңгҒігҒ§гҒ—гҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖпјҲгҖҺжқҫеҺҹзҘҗе–„и¬ӣзҫ©йӣҶгҖҸ第еӣӣе·»гҖҢзңҹдәәгҒ«гӮҲгҒӣгҒҰгҖҚгӮҲгӮҠпјү
ж…ҡ(гҒ–гӮ“)愧(гҒҺ)гҒ®еҝөгҒҷгӮүз„ЎгҒ„иҮӘеҲҶгҒ«жҖқгҒ„гҒҢиҮігӮӢгҒ°гҒӢгӮҠгҒ§гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ