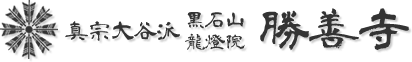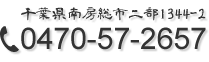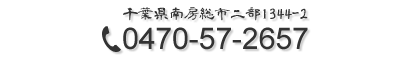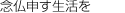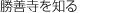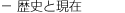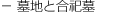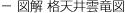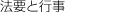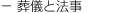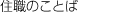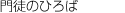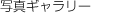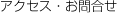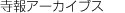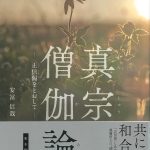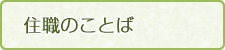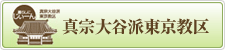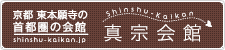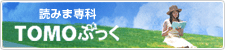2025.10.30
гҖҺзңҹе®—еғ§дјҪи«–пјҚжӯЈдҝЎеҒҲгӮ’гҒЁгҒҠгҒ—гҒҰпјҚгҖҸи‘—иҖ…пјҡе®үеҶЁдҝЎе“үгҖҖзҷәиЎҢпјҡжқұжң¬йЎҳеҜәеҮәзүҲ
д»Ҹж•ҷеҫ’гҒҢеё°дҫқгҒ—дҫӣйӨҠгҒӣгҒӯгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ¬д»Ҹе®қгғ»жі•е®қгғ»еғ§е®қгӮ’дёүе®қгҒЁиЁҖгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ•гҒЁгҒЈгҒҹдәәгҒЁгҒ•гҒЁгӮҠгҒ®жі•гҒЁгҒ•гҒЁгӮҠгҒ®жі•гӮ’гӮҒгҒ–гҒҷдәәгҖ…гҒ®йӣҶгҒ„гҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮгҖҢеғ§гҖҚгҒҜгҖҒеғ§дҫ¶гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ•гҒЁгӮҠгҒ®жі•гӮ’гӮҒгҒ–гҒҷдәәгҖ…гҒ®йӣҶгҒ„гҖҒгҖҢеғ§дјҪ(гҒ•гӮ“гҒҢ)гҖҚгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҜгҖҒд»Ҹжі•гӮ’иҒҙиҒһгҒ—иӘһгӮҠеҗҲгҒ„гҖҒгҒ•гҒЁгӮҠгҒ®жі•гҒ«з…§гӮүгҒ•гӮҢж—ҘеёёгӮ’з”ҹгҒҚгӮӢз§ҒгҒҹгҒЎзңҹе®—й–Җеҫ’гӮ’и«–гҒҳгҒҹжӣёгҒ§гҒҷгҖӮ
дё–дҝ—зҡ„гҒӘдҫЎеҖӨиҰігҒ«еҹӢжІЎгҒ—еҮәдё–й–“пјҲд»Ҹж•ҷпјүгҒ®дҫЎеҖӨиҰігӮ’еӨұгҒЈгҒҹз§ҒгҒҹгҒЎзңҹе®—й–Җеҫ’гҒҢгҖҒгҒқгҒ®еӣһеҫ©гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«иҮӘиҰҡгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„еҶ…е®№гҒҢгҖҒгҒ“гҒ“гҒ«иЁҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҺзңҹе®—еғ§дјҪи«–пјҚжӯЈдҝЎеҒҲгӮ’гҒЁгҒҠгҒ—гҒҰпјҚгҖҸгҖҖдё–дҝ—зҡ„дҫЎеҖӨе„Әе…ҲгҒ®жҷӮд»ЈпҪһзӣёеҜҫзҡ„дҫЎеҖӨиҰігҒӢгӮүзө¶еҜҫзҡ„дҫЎеҖӨиҰігҒё
дәҢгҖҮгҖҮе…«е№ҙе…ӯжңҲе…«ж—ҘгҖҒжқұдә¬гҒ®з§Ӣи‘үеҺҹгҒ§йҖҡз§°гҖҢз§Ӣи‘үеҺҹйҖҡгӮҠйӯ”дәӢ件гҖҚгҒҢиө·гҒ“гӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮзҠҜдәәгҒҜгғҲгғ©гғғгӮҜгҒ§жӯ©иЎҢиҖ…еӨ©еӣҪгҒ«дҫөе…ҘгҒ—гҖҒж¬ЎгҖ…гҒЁжӯ©иЎҢиҖ…гӮ’гҒҜгҒӯгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҖҒзҠҜдәәгҒҜеӨҡж•°гҒ®жӯ©иЎҢиҖ…гӮ’еҲғзү©гҒ§ж®әеӮ·гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮдёғдәәгҒ®ж–№гҒҢжӯ»дәЎгҒ—гҖҒеҚҒдәәгҒ®ж–№гҒҢиІ еӮ·гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®дәӢ件гӮ’еј•гҒҚиө·гҒ“гҒ—гҒҹйқ’е№ҙгҒҜгҖҒгҖҢеӢқгҒЎзө„гҒҜгҒҝгӮ“гҒӘжӯ»гҒӯгҒ°гҒ„гҒ„гҖҚгҒЁиЁҖгҒЈгҒҹгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®дәӢ件гҒҜгҖҒдё–дҝ—зҡ„гҒӘдҫЎеҖӨиҰігӮ’е„Әе…ҲгҒ—гҒҰгҖҒдәәй–“гҒЁгҒ—гҒҰе®ҲгӮӢгҒ№гҒҚгӮӮгҒ®гӮ’иҰӢеӨұгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜиҰӢиӘӨгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’з«Ҝзҡ„гҒ«зӨәгҒҷдәӢ件гҒ§гҒҷгҖӮзўәгҒӢгҒ«зӨҫдјҡгҒҜдәәй–“гҒ®йҒ“еҫізӯүгҒ®дё–дҝ—зҡ„гҒӘдҫЎеҖӨиҰігҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒеҪўжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҸгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒдё–дҝ—зҡ„гҒӘдҫЎеҖӨиҰігҒҜеӨ§еҲҮгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдё–дҝ—гҒ®дҫЎеҖӨиҰігӮ’и¶…гҒҲгҒҹгҖҒеҮәдё–й–“гҒ®дҫЎеҖӨиҰігҒ«гҒөгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒгҒҜгҒӘгҒҜгҒ гҒ—гҒҸиҝ·гҒҶгҒЁгҒ„гҒҶзҸҫе®ҹгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒЁиЁҖгҒҶгҒ®гӮӮгҖҒдё–дҝ—зҡ„гҒӘдҫЎеҖӨиҰігҒҜгҖҒзӣёеҜҫзҡ„гҒӘдҫЎеҖӨиҰігҒ§гҒӮгӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
зҸҫд»ЈгҒҜж је·®зӨҫдјҡгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеӢқгҒЎзө„гӮ„иІ гҒ‘з§ҹгҒЁгҒ„гҒҶдҫЎеҖӨиҰігҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒқгҒ®дҫЎеҖӨиҰігҒҜгҖҒжҷӮд»ЈгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеӨүиІҢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠз§ҒгҒҹгҒЎгҒҜгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®жҷӮд»ЈгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдҫЎеҖӨиҰігҒ«жҢҜгӮҠеӣһгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгҒ“гҒЁгҒӢгӮүз§ҒгҒҹгҒЎгҒҜгҖҒдё–дҝ—гҒ®дҫЎеҖӨиҰігӮ’и¶…гҒҲгҒҹиҖ…гҒ«гҒӘгӮүгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮд»ҘеүҚз§ҒгҒҜгҖҒж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жӣёгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
з§ҒгҒҹгҒЎгҒ®гҒ“гҒ®иә«гҒҜдё–дҝ—гҒ®дёӯгҒ«гҒӮгӮӢгҒ‘ гӮҢгҒ©гӮӮгҖҒдё–дҝ—гӮ’и¶…гҒҲгҒҹгӮӮгҒ®гҒ«зңјгӮ’й–Ӣ гҒӢгҒӘгҒ„гҒЁгҖҒгҒ©гҒҶгҒ—гҒҰгӮӮдё–дҝ—гҒ®дҫЎеҖӨиҰі гҒ®дёӯгҒ«зёӣгӮүгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒдәә й–“зҡ„гҒӘзү©е·®гҒ—гҒ гҒЁгҒӢгҖҒиҮӘе·ұгҒ гҒЁгҒӢгҖҒ гҒқгҒҶгҒ„гҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гӮ’дёӯеҝғгҒ«з”ҹгҒҚгҒҰгҒ—гҒҫ гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒҜгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫ гҒӘж„Ҹе‘ігҒ§дәәй–“гҒ®гҒІгҒҡгҒҝгҒ гҒЁгҒӢгҖҒзӨҫдјҡ гҒ®гҒІгҒҡгҒҝгҒ гҒЁгҒӢгҖҒгҒқгҒҶгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гӮ’гҒ„ гӮҚгҒ„гӮҚз”ҹгҒҝеҮәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ„гӮҸгҒ°жң¬е°ҠгҖҒжң¬еҪ“гҒ«е°Ҡ гҒ„гҒ“гҒЁгӮ’иҰӢеӨұгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“ гҒЁгҒҢгҖҒзҸҫд»ЈгҒ®еӨ§гҒҚгҒӘзү№еҫҙгҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ
пјҲе®үеҜҢдҝЎе“үгҖҺеё°дҫқдёүе®қпјҚд»Ҹж•ҷеҫ’гҒ®еӨ§ еҲҮгҒӘгӮҲгӮҠгҒ©гҒ“гӮҚпјҚгҖҸжқұжң¬йЎҳеҜәеҮәзүҲгҖҒ д№қпҪһдёҖгҖҮй Ғпјү
зҸҫд»ЈгҒҜдё–дҝ—гҒ®дҫЎеҖӨгҒҢеүҚйқўгҒ«еҮәйҒҺгҒҺгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҖҒе®—ж•ҷзҡ„гҒӘдҫЎеҖӨгӮ’иҰӢеӨұгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰдәәй–“гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®ж§ҳгҖ…гҒӘе•ҸйЎҢгҒҢеҮәгҒҰгҒҚгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
з§ҒгҒҹгҒЎзңҹе®—й–Җеҫ’гҒҜгҖҒж—ҘеёёгҒ®з”ҹжҙ»гҒ®дёӯгҒ§гҖҢжӯЈдҝЎеҒҲгҖҚгӮ„гҖҺеҫЎж–ҮгҖҸгӮ’жӢқиӘӯгҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒҜгҖҢжӯЈдҝЎеҒҲгҖҚгӮ„гҖҺеҫЎж–ҮгҖҸгӮ’гҒЁгҒҠгҒ—гҒҰгҖҒдё–дҝ—зҡ„гҒӘзү©гҒ®иҰӢж–№гҒЁз•°гҒӘгӮӢгҖҒгӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҒ®д»Ҹж•ҷгҒ«гӮҲгӮӢзү©гҒ®иҰӢж–№гӮ’еӯҰгӮ“гҒ§гҒ„гҒҸгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж„Ҹе‘ігҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒгҖҢжӯЈдҝЎеҒҲгҖҚгӮ’еӨ§еҲҮгҒӘгҒҠиҒ–ж•ҷгҒЁгҒ—гҒҰжӢқиӘӯгҒ—гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҺи“®еҰӮдёҠдәәеҫЎдёҖд»ЈиЁҳиҒһжӣёгҖҸгҒҜгҖҢзңҹе®—и«–иӘһгҖҚгҒЁгӮӮиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеӨ§еҲҮгҒӘгҒҠиҒ–ж•ҷгҒ§гҒҷгҖӮгҖҺи«–иӘһгҖҸгҒЁгҒҜеӯ”еӯҗгҒ®иЁҖиЎҢйӣҶгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒзү№гҒ«е°Ғе»әжҷӮд»ЈгҖҒжӯҰеЈ«гҒ«иҰӘгҒ—гҒҫгӮҢгҒҹдёҖгҒӨгҒ®жүӢжң¬гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжӯҰеЈ«гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰиҮӘгӮүгӮ’жҳ гҒ—еҮәгҒҷйҸЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжӣёзү©гҒ гҒӨгҒҹгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж„Ҹе‘ігҒ§гҖҺи“®еҰӮдёҠдәәеҫЎдёҖд»ЈиЁҳиҒһжӣёгҖҸгҒҢгҖҢзңҹе®—и«–иӘһгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҒҹгҒЁдјқгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
дё–дҝ—зҡ„гҒӘдҫЎеҖӨиҰігӮ’дҫқгӮҠеҮҰгҒЁгҒ—гҒҰз”ҹгҒҚгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒдҫӢгҒҲгҒ°гҒҠйҮ‘гӮ„еҗҚиӘүгӮ„зӨҫдјҡзҡ„гҒӘең°дҪҚзӯүгӮ’жң¬е°ҠгҒЁгҒҷгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒқгҒҶгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҜд»ҸгҒ®ж•ҷгҒҲгӮ’жң¬е°ҠгҒЁгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгҒҶгҒӘгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮз§ҒгҒ®дёҠгҒ«жӯЈдҝЎеҝөд»ҸгҒҢжҲҗгӮҠз«ӢгҒӨжҷӮгҖҒдё–дҝ—зҡ„гҒӘдҫЎеҖӨгҒӢгӮүеҮәдё–й–“гҒ®дҫЎеҖӨгҒёгҖҒгҒӨгҒҫгӮҠзӣёеҜҫзҡ„дҫЎеҖӨгҒӢгӮүзө¶еҜҫзҡ„дҫЎеҖӨгҒёгҒЁи»ўгҒңгӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ“гҒ«дәәз”ҹгҒ®ж–№еҗ‘гҒҢеҮәгҒҰгҒҸгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒҜеҝөд»ҸгҒ®жҷәж…§гҒ«гӮҲгӮӢз”ҹгҒҚж–№гҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮдәәзҹҘгҒ§гҒҜй ·гҒ‘гҒӘгҒ„гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—з§ҒгҒҹгҒЎгҒҜдәәзҹҘгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒ©гҒҶгҒ«гӮӮгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒд»ҸжҷәгҒ«з…§гӮүгҒ•гӮҢгҒҰз”ҹгҒҚгҒҰгҒ„гҒҸгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠдәәзҹҘгҒЁд»ҸжҷәгҒ®дәҢгҒӨгҒ®дёӯгҒ§з”ҹжҙ»гҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҖҺеҫЎж–ҮгҖҸгҒ§гҒҜгҖҢжң«д»Јз„ЎжҷәгҖҚпјҲзңҹе®—иҒ–е…ёе…«дёүдәҢй ҒпјүгҒЁиЁҖгҒҶгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҜжң«д»Јз„ЎжҷәгҒ®еҮЎеӨ«гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶдёҖзӮ№гҒ«з«ӢгҒЎгҖҒгҒ“гҒ®иЈҹе©ҶгӮ’з”ҹгҒҚгҒҰгҒ„гҒҸгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒҢе…¶гҒ®з”ҹгҒҚж–№гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдәәз”ҹгҒ®ж–№еҗ‘гҒҢдё–дҝ—гҒӢгӮүе®—ж•ҷгҒёгҒЁи»ўгҒҡгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
дё–дҝ—гҒӢгӮүе®—ж•ҷгҒёгҒЁи»ўгҒҳгҒҰгҒ„гҒҸгҒ“гҒЁгӮ’гҖҒдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гҒҜеӣһ(гҒӢгҒ„)еҝғ(гҒ—гӮ“)гҒЁиЁҖгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгӮӯгғӘгӮ№гғҲж•ҷгӮӮеӣһ(гҒӢгҒ„)еҝғ(гҒ—гӮ“)гҒЁиЁҖгҒ„гҒҫгҒҷгҒ—гҖҒд»Ҹж•ҷгҒ§гҒҜеӣһ(гҒҲ)еҝғ(гҒ—гӮ“)гҒЁе‘јгҒігҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгҒ§гҒҜгҖҒзңҹе®—гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒқгҒ®еӣһеҝғгҒЁгҒҜгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгҒ“гҒЁгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮиҰӘйёһиҒ–дәәгҒҜгҖҺе”ҜдҝЎйҲ”ж–Үж„ҸгҖҸгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҢгҖҢеӣһеҝғгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҒҜгҖҒиҮӘеҠӣгҒ®еҝғгӮ’гҒІгӮӢгҒҢгҒҲгҒ—гҖҒгҒҷгҒӨгӮӢгӮ’гҒ„гҒҶгҒӘгӮҠгҖҚпјҲзңҹе®—иҒ–е…ёдә”дә”дәҢй ҒпјүгҒЁиӘ¬гҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ•гӮүгҒ«иҰӘйёһиҒ–дәәгҒ”иҮӘиә«гҒ®еӣһеҝғгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгҖҺж•ҷиЎҢдҝЎиЁјгҖҸгҖҢеҫҢеәҸгҖҚгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҢгҒ—гҒӢгӮӢгҒ«ж„ҡзҰҝйҮҲгҒ®йёһгҖҒе»әд»ҒиҫӣгҒ®й…үгҒ®жҡҰгҖҒйӣ‘иЎҢгӮ’жЈ„гҒҰгҒҰжң¬йЎҳгҒ«её°гҒҷгҖҚпјҲзңҹе®—иҒ–жӯӨдёүд№қд№қй ҒпјүгҒЁиҝ°гҒ№гҒҰгҒҠгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®еӣһеҝғгҒЁгҒҜгҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜжң¬йЎҳгҒ«её°гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮиӘ“гҒҲгҒҰиЁҖгҒҲгҒ°гҖҒд»ҠгҒҫгҒ§ж №з„ЎгҒ—иҚүгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзҠ¶ж…ӢгҒ«гҒӮгҒЈгҒҹиҮӘеҲҶгҒҢгҖҒеҲқгӮҒгҒҰжң¬йЎҳгҒЁгҒ„гҒҶеӨ§ең°гҒ«ж №гӮ’гҒҠгӮҚгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгӮӮгҒЈгҒЁе…·дҪ“зҡ„гҒ«иЁҖгҒҲгҒ°гҖҒеҝөд»ҸгӮ’з”ігҒҷиҖ…гҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
иҰӘйёһиҒ–дәәгҒ”иҮӘиә«гҒҜгҖҒжҜ”еҸЎеұұгҒ®еӨ©еҸ°е®—гҒ§дҝ®иЎҢгҒ•гӮҢгҒҰгҖҒгҒқгҒ®дҝ®иЎҢгҒ®дёҖеҲҮгӮ’ж”ҫж“ІгҒ—гҒҰгҖҒ法然дёҠдәәгҒ®гӮӮгҒЁгҒёиЎҢгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеҝғгҒҢзҝ»гӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҒҰгҖҒиә«гҒҢзҝ»гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠеӣһеҝғгҒЁгҒҜи»ўиә«гҒ®гҒ“гҒЁгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒҜдёҖгҒӨгҒ®жҠҪиұЎзҡ„гҒӘзҗҶи«–гҒҢгҖҒжҠҪиұЎзҡ„гҒӘеҲҘгҒ®зҗҶи«–гҒ«еӨүгӮҸгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҖӮжң¬еҪ“гҒ«иҮӘеҲҶгҒҢз«ӢгҒӨгҒ№гҒҚеӨ§ең°гҒ«ж №гӮ’гҒҠгӮҚгҒҷгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮгҒ•гӮүгҒ«иЁҖгҒҲгҒ°гҖҒдёҖз·’гҒ«еҝөд»Ҹз”ігҒҷиҖ…гҒЁе…ұгҒ«жӯ©гҒҝгҒ гҒҷгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҝөд»Ҹз”ігҒ—гҖҒгҖҺжӯЈдҝЎеҒҲгҖҸгӮ’еӢӨгӮҒгҖҒд»Ҹжі•гӮ’иҒҙиҒһгҒ—иӘһгӮҠеҗҲгҒҶгҖӮгҒ“гӮҢгҒҢгҖҒеҮәдё–й–“пјҲд»Ҹж•ҷпјүгҒ®дҫЎеҖӨиҰігҒ«и§ҰгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ