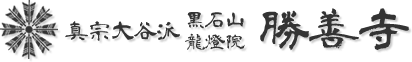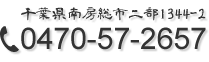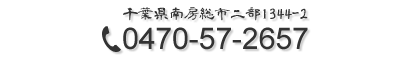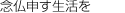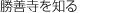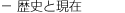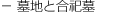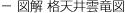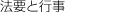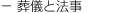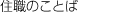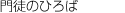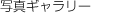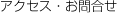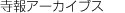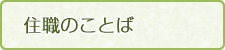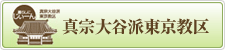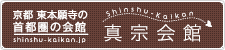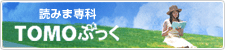2023.01.01
дҪҸиҒ·гҒ®гҒ“гҒЁгҒ°
2021.11.03
еӨ©е‘ҪгҒ«е®үгӮ“гҒҳгҒҰдәәдәӢгӮ’е°ҪгҒҸгҒҷ
2021.08.04
жҡ‘дёӯгҒҠиҰӢиҲһгҒ„з”ігҒ—гҒӮгҒ’гҒҫгҒҷгҖӮ
2021.05.19
гҒҫгҒҡеҝөд»Ҹз”ігҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
2021.04.04
иҰӘйёһиҒ–дәәгҒЁиҒ–еҫіеӨӘеӯҗ
2020.12.31
謹иіҖж–°е№ҙ
2020.09.10
жӮӘйҮҚгҒҸйҡңеӨҡгҒҚгӮӮгҒ®гӮҲ
2020.03.19
гҖҺжҲҝж—Ҙж–°иҒһгҖҸжҳҘгҒ®еҪјеІёзү№йӣҶ
2020.03.10
гҒҠеҪјеІёгӮ’еүҚгҒ«гҒ—гҒҰ
2020.03.08